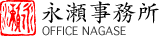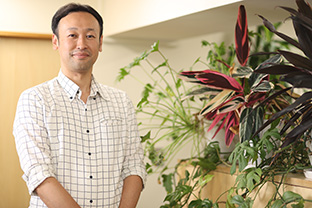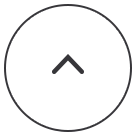他の商談会と違って、すごく面白いなって思っています

神奈川県を中心に地域に密着し、日常のおいしい食材選びに力を入れている創業88年のローカルマーケット、OONOYA・大野屋商店。関東圏でスーパー4店舗とセレクトショップ3店舗を展開しています。令和6年4月にはOONOYA新綱島店(横浜市)をあらたにオープン。
今回は、これら店舗を運営する株式会社大寿の代表取締役ながらバイヤーもされている大野孝将さんに、「食卓にあがる商品に求めるもの」についてお話を伺います。
「高級品ではなく、高品質で日常使いできる」地方の食材を扱う
大学を2002年に卒業しました。最初は実家のスーパーマーケットを継ぐつもりはなく、魚が好きだったので漁師か魚屋さんになりたいと思っており、悩んだ結果、築地の水産会社に就職させていただきました。そのあとデパ地下で働き、横浜の髙島屋や大阪の近鉄百貨店で3年ちょっと経験を積みました。魚を切ったり、お客様と接したり、マグロの解体ショーをしたりもしましたよ。その後、実家の会社に戻り、最初は魚の現場で働き、店長・専務を経て社長になりました。
今、スーパー4店舗、セレクトショップを3店舗を展開しています。スーパーの“OONOYA”は、買い物をして楽しい・食べて美味しい・地域に密着した食のローカルマーケットで、セレクトショップの“大野屋商店”は、調味料や乾物・お菓子・日配品など全国各地のローカルな加工食品をセレクトした専門店です。どちらの店の商品も、全国を巡って自分たちの足と目で確かめて商品仕入れを行っています。
2つの業態を運営していますが、最初は試行錯誤でした。大野屋商店もスーパーの延長のような感じで考えていましたが、隣に大きなスーパーがあったので、セレクトした商品を扱うことにしました。最初は野菜も売っていましたが、最終的に地域食材に特化した加工食品に絞りました。4、5年かけて今の規模まで持っていきました。
また武蔵小杉(川崎市)という地域を例にすると、イトーヨーカドーさん、マルエツさん、ダイエーさん、成城石井さん、紀ノ国屋さんなどがあります。その中で、「毎日が楽しく、普段使い」の商品を提供しています。「高級品ではなく、高品質で日常使いできる」地方の食材を扱っていて、他社のお店とは品揃えや世界観で差別化をしています。
日本全国を駆け巡り吟味した、本物の食材を食卓へ
商品仕入れは私とバイヤー、今7店舗ありますが各店舗の店長で行っています。例えば、私が地方に行って100種類ほど商品を見つけてきて、毎月10人ほど集まって検討するような感じです。店舗ごとに商品を選定し、地域性や客層に合わせて決めています。「この店はこの商品やります、こっちの店はこの商品やりません」みたいに、商品の仕入れの権限は店長にあります。やはりそれぞれの店舗に地域性がありますので、それは店長の采配で決めるのがいいのかな、と。そうしたほうがやりがいを持ってやれるのかなと思います。
私自身は社長として経営、バイヤー、販促の3つが主な仕事です。店舗運営は店長に任せています。特に力を入れているのは商品の開発というか、発掘です。経営者としての仕事もありますが、お客様に喜んでもらえる商品を見つけることにやりがいを感じています。
お店の売れ筋商品は、すぐに食べられるものの需要が高まっています。お惣菜やカレーなどの回転が良くなっています。一方で、基礎調味料など家で料理をする人向けの商品も大切にしています。また、「ちょい足し」の食材も人気です。
ただ、すぐ食べられる商品は流行り廃りが激しいので、常に新しい提案をしていく必要があります。
家で料理をする人が減っていると感じます。運動会のお弁当でも、手作りではなくセミレディの食材を使う家庭が増えています。便利さは否定できませんが、大切な日にも外食や中食が増えていることに少し違和感を感じていますね。
でも、これは時代の流れでもあるので、家庭での食事や会話を大切にする文化を残しつつ、現代のニーズにも応えていく必要があると考えています。
日本の食文化を残す商品を応援したい
店頭で採用するポイントは、まず大量生産ではない商品、添加物をなるべく使用していない商品を求めています。ただし、完全なオーガニックスーパーを目指しているわけではありません。
また、日本の食文化を残していきたいという思いがあるので、そういったエッセンスが入った商品を探しています。そういった商品は、なんかこう、 すごく応援したいなって。最近では、佃煮屋さんが技術を活かして作った生炊きのふりかけなど、伝統的な食品を現代風にアレンジした商品が良かったですね。
地域商材はもちろんなのですが、汎用性が高くて、和だけれど洋風にアレンジできるとか、お客さんにいろいろな食べ方を提案できる商品を重視しています。
うちのお店に限って言えば、大野屋は「日常使いの中」の楽しくて美味しいものを探しているので、特定の「〇〇県だから」というのは強くないかもしれません。やっぱり最初に美味しい商品があって、最後に「実はこれは〇〇県で作っています」って。地域産品ってそういうポジションでいいんじゃないかなって私は思います。まずは美味しいのかどうか、自分の家のテーブルにそれがあるシーンが浮かぶかどうか、提案ができるかどうかってとこだと思います。
商品にちゃんと付加価値がついていて、価格と価値を比較した時に、価格よりも価値がちゃんと上をいってるかどうかというのは、全ての商品においてやっぱりしっかり見極めていかなくちゃいけないかなと思っています。価格っていうより価値です。美味しくないと。でも、ちょっと美味しいぐらいですごい高いじゃダメなんです。 めちゃくちゃ美味しくて結構な値段であれば、それはそれで価値があるかなと思います。ですから、商品辞退が他の地域のものよりも美味しく作られているかが大事です。

バイヤーズ・ガイドの商談会では、新しい商品との出会いに期待
バイヤーズ・ガイドさんの商談会は他の商談会と違って、ちょっと細分化されたご案内も多くて、すごく面白いなって思っています。宇和島とかありましたよね。くくりが県じゃなくて、島や市区町村。まだ知られてないものが地域ごとにいっぱいありそうですし、新しい商品との出会いに期待しています。
あと、事業者さんのFCP展示会・商談会シートが見られるようになっていることもいいですね。FCP展示会・商談会シートが見られる見られないって大きいんですよ。カタログだけじゃわからない。FCP展示会・商談会シートをしっかり作り込んでいる企業って ちゃんとしているなって私は思っています。1番わかりやすくて、大切なことがちゃんと載っているので、きっちり見るようにしています。
最後に綺麗にまとめると、バイヤーズ・ガイドさんには、「これからも地方の事業者さんを信じてください」と言いたいです。